PR
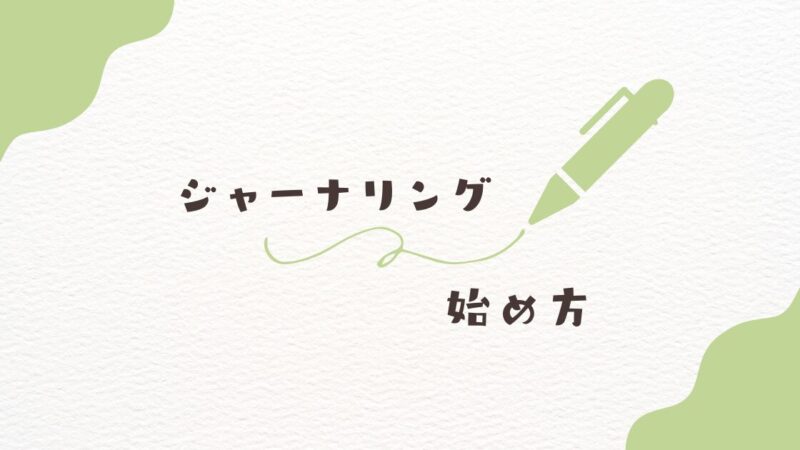
「ジャーナリングを始めてみたいけど、何から手をつければいいの?」
そんな悩みを抱えていませんか。
ジャーナリングとは、自分の内面を書き出すことで、感情の整理・ストレス解消・自己理解の向上などに役立つメンタルケア手法です。
近年は「書く瞑想」としても注目されており、日々のモヤモヤや、人に話しにくい気持ちを落ち着いて整理する手段として取り入れる人が増えています。
とくに、INFPやHSPのように感受性が強く、頭の中で考えごとが渋滞しやすいタイプにとって、ジャーナリングは「感情の避難場所」として大きな助けになります。
この記事では、初心者でも無理なく続けられるジャーナリングのやり方と効果、注意点までを、筆者の体験とINFP視点を交えながら解説します。
先に結論を知りたい方へ
- ジャーナリングとは:感情や思考を書き出して自己理解を深める「書くセルフケア習慣」
- 日記との違い:日記は出来事の記録、ジャーナリングは内面の整理や意味づけが中心
- 初心者向けの始め方:ノートとペンを用意し、書く時間を決めて、完璧を求めず自由に書く
- 効果:ストレス軽減、創造力UP、自己理解と自己肯定感の向上、仕事や将来設計の整理にも役立つ
- 注意点:ネガティブな感情の再体験には注意。心の不調が強い場合は専門家の助けを優先
ジャーナリングと日記の違いとは?

「ジャーナリングって、日記と何が違うの?」という疑問は、多くの人が最初に抱くものです。
日記とジャーナリングの違いを、以下の表にまとめました。
| 項目 | 日記 | ジャーナリング |
|---|---|---|
| 目的 | 出来事の記録 | 感情・思考・気づきの言語化 |
| 書く内容 | 「何があったか」 「誰と何をしたか」 | 「なぜそう思ったか」 「何を感じたか」 「そこから何を学んだか」 |
| 書き方 | 時系列に淡々と書く | 自由な形式で書く (箇条書き・図・イラストもOK) |
日記は主に事実の記録です。一方で、ジャーナリングは自分の内面と向き合う行為です。
たとえば、日記では「今日は友人とランチをした」と書きます。
ジャーナリングでは「友人と話して嬉しかった。悩みを素直に話せて、心が軽くなった」といった気持ちの整理や内省が中心になります。
INFPやHSPとジャーナリングの相性
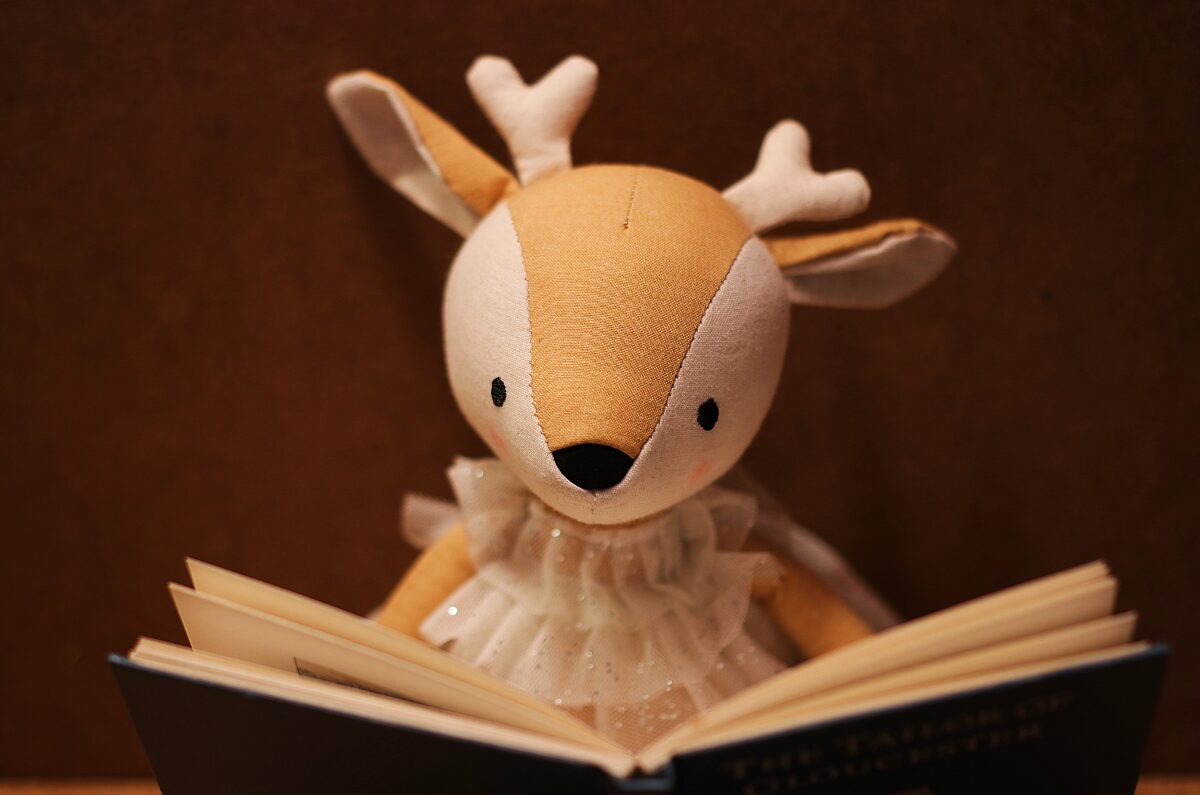
INFPやHSPのように、感受性が強く、頭の中で物事を何度も反芻しやすい人は、日常の小さな出来事でも心の負担を抱えやすい傾向があります。
- 相手の一言が気になって、何度も思い出してしまう
- その場では言えなかった言葉を、後から頭の中で繰り返してしまう
- 集団の空気や人間関係を気にしすぎて、疲れがたまりやすい
ジャーナリングは、こうした「頭の中でぐるぐるしている思考や感情」を、一度ノートに避難させる役割を持ちます。
- 思ったことをそのまま書いてみる
- 何がつらかったのかを言葉にしてみる
- 本当はどうしたかったのかを整理してみる
このプロセスを通じて、感情のボリュームが少し落ち着き、次の行動を選びやすくなります。
INFPやHSPの気質については、以下の記事で詳しく整理しています。
- INFPとHSPの共通点・違い・向いている仕事を解説した記事
≫ INFPでHSPかも?共通点・違い・向いてる仕事を解説 - 「INFPはなぜ日本に合わないのか?」を文化や価値観の観点から整理した記事
≫ INFPはなぜ日本に合わないの?文化と価値観のすれ違いを解説
ジャーナリングは、こうした自己理解記事で見えてきた「自分の傾向」を、日常の中で検証していくツールとしても役立ちます。
初心者でも迷わないジャーナリングのやり方とは?

ジャーナリングは、正解のない「自分との対話」です。
書き方に厳密なルールはありませんが、始めやすく、続けやすいステップを押さえることで効果を感じやすくなります。
ここでは、初心者向けにジャーナリングのやり方を4ステップで解説し、朝と夜用のテンプレートも紹介します。
1. お気に入りのノートとペンを用意する
まずは「自分だけの特別なノート」を選びます。
シンプルなノートから、おしゃれなハードカバーノートまで、どのような形でも構いません。
大切なのは、「手に取って開きたくなるかどうか」です。
筆者は、質感の良い紙と万年筆を用意したことで、「書くこと」が一つの楽しみになりました。
スマホアプリやiPad+スタイラスペンで始めても問題ありません。
デジタルはプライバシー保護や検索性の高さがメリットです。
2. リラックスできる時間と場所を決める
「書こうと思っていたのに、気づいたら一日が終わっていた…」
というパターンを避けるには、あらかじめ「書くタイミングを決めておく」ことが役立ちます。
- 朝の静かな時間に、その日の気持ちを整える
- 夜寝る前に、その日を振り返りながら感情を言葉にする
- 週末の午後に、コーヒーを飲みながらゆったり振り返る
書く環境も意外と大切です。
お気に入りの音楽を流したり、アロマや飲み物を用意したりして、「書くことに集中できる小さな空間」をつくってみてください。
3. 書き始めるときのコツとは?
「何を書いたらいいのか分からない…」という悩みを持つ人は多いです。
ただし、ジャーナリングに「うまく書く」必要はありません。
初心者向けのコツを整理すると、次のようになります。
- 完璧を求めない:誤字や文法ミスを気にしない
- テーマを軽く決める:気分・出来事・感謝したことなどから選ぶ
- 時間を区切る:最初は5分、慣れたら10〜15分
「今日の気分はどうだったか」「どんなときに嬉しいと感じたか」といったシンプルな問いから始めると、言葉が出やすくなります。
手書きだと続きにくい場合、最初からアプリを活用する方法もあります。
書くテーマを考える時間が負担になりやすい人は、質問に沿って入力できる形の方が始めやすいです。
≫ Awarefyの評判・口コミは?向き不向きを確認する
4. 続けるための工夫は?
ジャーナリングは、自分に合った形で無理なく続けることが大切です。
挫折しそうになったときに役立つ工夫を挙げておきます。
- 書く時間を固定する(例:朝食後、寝る前)
- ノートをデコる(カラーペン・マスキングテープ・シールなど)
- 週1でもOKと決める(完璧主義を弱める)
- 書けない日があっても、自分を責めないルールをつくる
「楽しめているかどうか」を1つの目安にすると、習慣化しやすくなります。
5. 朝5分・夜5分のかんたんテンプレート
何を書けば良いか迷うときは、あらかじめ「型」を決めておくとスムーズです。
朝と夜、それぞれ5分で使えるテンプレート例を紹介します。
朝5分ジャーナリングの例
- 今日の気分は?
- 今日やりたいことを3つ挙げる
- 不安に感じていることと、その対策を1つ書く
夜5分ジャーナリングの例
- 今日うまくいったことを3つ挙げる
- 心に引っかかった出来事と、そのときの気持ちを書く
- 明日の自分にひと言メッセージを書く
これらは箇条書きでも十分です。
慣れてきたら、自分用に項目を入れ替えたり、質問を増やしたりして、自分なりのテンプレートへ調整していきましょう。
ジャーナリングのテーマをもっと増やしたい場合は、初心者から経験者まで使えるお題をまとめた記事も用意しています。迷ったときの「ネタ帳」として活用できます。
≫ 毎日使えるジャーナリングテーマを紹介!お題&テンプレート一覧
ジャーナリングにはどんな効果があるの?

「書くだけで本当に効果があるのだろうか」と感じる人も多いはずです。
実際に続けている人の多くが、気持ちの整理や自己理解の深まり、行動の変化を実感しています。
ここでは、代表的な効果を4つに分類して紹介します。
1. ストレスの軽減・感情の整理ができる
言葉にできないまま心にモヤモヤを溜め込んでいると、ストレスは徐々に積み重なります。
ジャーナリングは、感情を「言語化」することで、脳の整理整頓を助けます。
- イライラや不安を紙に書くことで、客観視しやすくなる
- どの場面で疲れているのか、パターンが見えやすくなる
- 自分にとって負担の大きい人間関係や状況が分かってくる
American Psychological Association(APA)でも、書くことによる自己省察がメンタルヘルスの改善に有益であると報告されています。
ジャーナリングは、科学的にも裏付けのある「書くセルフケア」として注目されています。
2. 創造力が育ち、アイデアが浮かびやすくなる
ジャーナリングは、頭の中の「未整理な思考」を次々と外に出す作業です。
- 頭の中の混乱が整い、思考の余白が生まれる
- 新しい発想が浮かびやすくなる
- ブログ・創作・仕事のアイデアが自然と集まってくる
筆者もブログ運営の際、「何を書こうか」と悩んだときに、ジャーナリングノートを見返すことでネタを拾うことが増えました。
3. 自己理解・自己肯定感が深まる
自分の気持ちや考えを書き続けると、「どんな価値観を大事にしているか」が見えてきます。
- 嫌だと感じていたことが、実は無理をしていたサインだった
- うまくいかなかったと思っていたが、小さな成長は積み重なっていた
- 心からやりたいことの共通点が見えてくる
こうした気づきが蓄積されることで、自己肯定感が少しずつ育っていきます。
4. 習慣としての達成感と前向きなループが生まれる
「今日も書けた」「昨日より気持ちが楽だ」といった小さな成功体験が、習慣としての自信につながります。
- 毎日のジャーナリングが「自分を大切に扱う時間」になる
- 少しずつ変化している感覚を持てる
- 書くことが癒しになり、生活にリズムが生まれる
気分の浮き沈みだけでなく、創造性や行動パターンにも好影響を与えるのがジャーナリングの特徴です。
ジャーナリングを続けても効果を実感しにくい場合に考えたいポイントは、別の記事で詳しく整理しています。
書き方やタイミングの見直しが必要なケースについて知りたい場合は、そちらも参考になります。
≫ ジャーナリングをしても効果が出ない理由と見直しポイントを解説
仕事や将来設計でジャーナリングを活かすには?

ジャーナリングはメンタルケアだけでなく、仕事や将来設計にも応用できます。
とくに、INFPのように「意味や納得感」を重視するタイプは、頭の中で条件や理想を考えすぎて動けなくなることが少なくありません。
ここでは、働き方や在宅ワークに関心がある人に向けて、実務的な活用例を3つ紹介します。
1. 仕事で疲れた日の振り返りに使う
仕事で強い疲れを感じた日のジャーナリングでは、次のような項目を書き出すと原因が見えやすくなります。
- どの場面で一番疲れたか
- その場面で、何を考え、どんな気持ちになったか
- 同じ状況を少しラクにするために試せそうな工夫
この振り返りを続けると、自分にとって負担の大きい業務・人間関係・環境の特徴が見えてきます。
「INFPはなぜ日本の職場で疲れやすいのか」を整理した記事と合わせて読むと、パターンの理解が進みます。
≫ INFPはなぜ日本に合わないの?文化と価値観のすれ違いを解説
2. 働き方の条件を書き出す「思考整理ノート」として使う
転職や在宅ワークを検討するときは、いきなり求人サイトを見る前に、「条件の棚卸し」をしておくと混乱しにくくなります。
たとえば、次のような項目をノートに分けて書き出します。
- 仕事内容で譲れないこと・避けたいこと
- 人間関係やコミュニケーションのスタイル
- 収入や働く時間、在宅の割合などの現実的な条件
このような「思考整理ノート」としてのジャーナリングは、仕事や将来を考える記事(INFPの適職・現実的な働き方など)と相性が良いです。
思考整理ノートの具体的な書き方やテンプレートについては、別の記事で詳しくまとめる予定です。
働き方や転職で迷うときの「土台づくり」として使えます。
3. ブログや発信のネタ帳として使う
もしあなたが「書くこと」に少しでも手応えを感じるなら、ジャーナリングノートを「ネタ帳」として扱ってみてください。
- 日々のモヤモヤした感情
- 困った経験と、そのとき試した工夫
- 誰かに聞いてほしかった小さな気づき
これらは、あなたと同じように悩む誰かにとっての「貴重な情報」になります。
INFPにとって、言葉はただの記録ではありません。磨けば光る才能です。
ノートに閉じ込めていた言葉を、Web上に「静かな仕事場」として開放する。
それだけで、将来の働き方の選択肢が大きく広がります。
言葉を「資産」に変える準備
特別なスキルは不要です。「書く習慣」さえあれば、在宅で収益を生む土台は作れます。
誰にも会わずに運営できるブログの始め方は、以下に図解でまとめています。
ジャーナリングの注意点やデメリットはある?

ジャーナリングはメリットの多い習慣ですが、書き方や内容によっては逆効果になる場合もあります。
ここでは、注意しておきたいポイントを2つの視点から整理します。
ネガティブな感情を繰り返すと、かえって落ち込むことも
「辛かったこと」「悲しかった出来事」「怒り」など、感情をそのまま書き出すことは一見良いことのように思えます。
ただし、ネガティブな内容ばかりを繰り返し書いていると、感情が強化・再体験されてしまうことがあります。
- 何度も同じ怒りを書き続ける
- 自分を責める言葉ばかりになる
- 読み返すたびに苦しくなる
この状態が続くと、ジャーナリングが癒しではなく、感情のループを深める行為になります。
対策としては、ネガティブな感情を書いたあとに、
- ではどうしたいか
- 今できることは何か
といった問いを一行だけ添えると、思考が少しずつ前向きな方向へ動きやすくなります。
精神的な不調がある場合は専門家のサポートを
うつ病や強い不安症状など、精神的な問題を抱えている場合、自己流で感情を深掘りしすぎると、症状を悪化させるリスクがあります。
- ネガティブな思考が止まらなくなる
- 過去のトラウマが蘇りやすくなる
- 自責や無力感が強まる
心当たりがある場合は、無理にジャーナリングを続けるのではなく、心理カウンセラーや医師の助言を優先することが大切です。
ジャーナリングはあくまでセルフケアの一つです。
症状が重い場合は、専門的な治療と併用する形で取り入れることをおすすめします。
【体験談】実際に続けて感じた、ジャーナリングの効果

理論だけではイメージしにくい部分もあるため、筆者の体験を簡単に紹介します。
自己肯定感が少しずつ育った
元々、自分に自信がなく「これでは足りない」と感じやすいタイプでした。
ジャーナリングを始めてから、「できたこと」「小さな進歩」に意識を向ける習慣がつきました。
ノートには、次のようなことを書いていました。
- 早起きできた
- 10分だけ掃除ができた
- ブログのネタをメモできた
どれも小さな出来事ですが、「何もできていない」と感じていた日は少しずつ減り、自分を責める回数も少なくなりました。
頭の中が整理されて、ブログや仕事のヒントが浮かぶように
ジャーナリングは「思考のデトックス」としても機能します。
- やらなければならないタスク
- 気になっている人間関係のこと
- 将来への漠然とした不安
こうした内容を一度ノートに吐き出すと、頭の中に余白が生まれます。
結果として、
- ブログのテーマを思いつきやすくなった
- 記事構成が組み立てやすくなった
- 無駄なタスクを減らしやすくなった
といった変化がありました。
自分の声を確認する時間を持つことで、周囲に振り回されにくくなった感覚もあります。
よくある質問(FAQ)

ジャーナリングについて、よくある質問をまとめました。
Q1. ジャーナリングにおすすめのノートはありますか?
おすすめしやすいノートとして、次のようなものがあります。
- 無印良品「文庫本ノート」:持ち運びやすく、シンプルなデザイン。紙質がなめらかで、日常使いに向きます。
≫ 無印良品の公式サイトはこちら - ミドリ「MDノート」:「書くことそのものを楽しむ」ために作られたノート。書き心地と紙質のバランスが良いです。
書きやすさは、継続のモチベーションに直結します。
可能であれば文具店などで実物を手に取り、書き心地を試してから選ぶと安心です。
Q2. 毎日書く必要はありますか?
必ずしも毎日書く必要はありません。
プレッシャーを強く感じる場合は、「週に1回でもOK」と決めてしまった方が続きやすいです。
- 気分が乗らない日は休む
- 書けなかった翌日に「また始めれば良い」と考える
このくらいのゆるさで続ける方が、長期的には安定します。
Q3. 書く内容が思いつかないときはどうすれば?
書く内容が浮かばないときは、「思いつかない」とそのまま書いてしまっても問題ありません。
質問形式のテンプレを使う方法もあります。
- 今日の気分はどうか
- 嬉しかったことは何か
- 気になっている出来事は何か
- 自分にかけたい言葉は何か
文章だけでなく、箇条書きや簡単な図・矢印などを混ぜても構いません。
テーマが欲しくなったときは、ジャーナリングテーマを一覧で紹介している記事も参考になります。
≫ 毎日使えるジャーナリングテーマを紹介!お題&テンプレート一覧
Q4. 手書きとデジタル、どちらがいい?
手書きとデジタルには、それぞれメリットがあります。
| 手書きジャーナリング | デジタルジャーナリング |
| 書く動作によって気持ちが落ち着きやすい | 思いついたときすぐ書ける |
| 記憶に残りやすい | 検索・整理がしやすい |
| アナログの質感を楽しめる | 写真・音声・リンクなども一緒に残せる |
| ノートが増えていく楽しみがある | データで保存・バックアップが取りやすい |
どちらが合うかは人によって違います。
最初はどちらか一方で試し、必要に応じて組み合わせて使う形でも問題ありません。
まとめ|今日から「書く習慣」を始めてみよう!

ジャーナリングは、感情や思考を言語化するだけの、シンプルで負担の少ないセルフケア手法です。
特別な才能や高価な道具を用意しなくても、ノートとペンがあれば始められます。
最後に要点を整理します。
- ジャーナリングの目的は、出来事の記録ではなく感情と意味づけの整理
- 朝5分・夜5分の短時間でも、ストレス軽減や自己理解の深まりにつながる
- INFPやHSPのように情報量が多い気質ほど、頭と心の避難場所として効果を感じやすい
続けるうえで大切なのは、完璧な文章よりも、記録したい感情や気づきを残す姿勢です。
書けない日があっても、翌日から軽い気持ちで再開できれば十分だと考えたほうが習慣化しやすいです。
ジャーナリングは、仕事の振り返りや将来設計、ブログなどの発信にも直結します。
ノートの中で見つかったパターンやテーマが、働き方の見直しや在宅ワークの一歩につながる場合も少なくありません。
まずは今日、1行だけでもペンを動かしてみてください。
その1行が、あとから読み返せる思考のログになり、いつかあなたを守る「軸」になっていきます。
続けられるか不安な方へ
ノートで気軽に続けられる人は、手書きのままで十分です。
一方で、書く前に考え込んで止まりやすい場合は、質問に沿って入力できるアプリへ切り替えると習慣が安定しやすくなります。
Awarefyが合う人・合わない人、無料で試す流れ、有料へ切り替えるときの注意点は次の記事で整理しています。
≫ Awarefyの評判・口コミと向き不向きを確認する
次に読むと役立つ記事
- INFPやHSPの気質を整理した記事(感受性の強さと生きづらさの背景を知りたい人向け)
≫ INFPでHSPかも?共通点・違い・向いてる仕事を解説 - INFPが日本社会で違和感を覚えやすい理由を整理した記事
≫ INFPはなぜ日本に合わないの?文化と価値観のすれ違いを解説 - ジャーナリングのテーマをまとめた記事(お題が欲しいとき用)
≫ 毎日使えるジャーナリングテーマを紹介!お題&テンプレート一覧 - 仕事や将来に迷ったときのための「思考整理ノート」記事
≫ 思考整理ノートで迷いを減らす|INFPが在宅自立に近づくためのノート術